国会といえば、日本の政治の中心。
しかし、その内部には一般常識からかけ離れた慣例が数多く存在します。
今回は、そんな国会の「信じられない慣例」を徹底的にリサーチしてみました。
信じられない慣例その1:国会での「くん付け」の謎

国会中継を見ていると、議員同士が「〇〇くん」と呼び合う場面をよく目にします。
これは一体なぜなのでしょうか?
実は、この「くん付け」には長い歴史があります。
明治時代の第1回帝国議会から続く伝統で、議員同士の対等な関係を示すために始まったとされています。
この慣習の起源は、幕末の教育者・吉田松陰にまで遡ると言われています。
松陰は、身分の異なる塾生たちが対等に議論できるよう「君」という呼称を用いたとされ、その精神が明治の国会にも引き継がれたのです。
現在でも、衆議院規則には「議員は、互いに敬称を用いなければならない」と定められており、参議院先例録にも「議員は、議場または委員会議室においては互いに敬称として『君』を用いる」と明記されています。
しかし、この慣例に対しては批判の声も上がっています。
「くん」という呼称が年少者や目下の者に使われることが多い現代では、違和感を覚える人も少なくありません。
特に、女性議員に対して「くん」付けで呼ぶことへの違和感は強く、性別に関係なく使用できる新たな敬称の導入を求める声もあります。
信じられない慣例その2:議員服装規定の意外な実態

国会議員の服装にも、驚くべき規定があります。
本会議場では上着の着用が義務付けられており、クールビズ期間中でも例外ではありません。
さらに、女性議員のパンプスも、つま先やかかとが露出するデザインは好ましくないとされています。
これらの規定は「議場にふさわしい品位ある服装」を求める先例に基づいていますが、現代の感覚とはかけ離れている面もあります。
特に興味深いのが、沖縄選出の議員による「かりゆしウェア」の着用です。
衆議院では許可されていますが、参議院では上着着用の規定があるため、かりゆしウェアの上にスーツのジャケットを羽織るという奇妙な光景が見られることもあります。
この矛盾した状況は、地域の文化を尊重しつつ、国会の伝統的規範を守ろうとする苦肉の策と言えるでしょう。
信じられない慣例その3:デジタル時代に逆行?電子機器使用制限

デジタル化が進む現代社会において、国会の電子機器使用制限は時代錯誤と言わざるを得ません。
本会議場ではパソコンやタブレット端末の持ち込みが禁止されており、議員は全て紙の資料で質問や答弁を行わなければなりません。
この規制の背景には、1990年代に携帯電話の着信音が審議の妨げになったという経緯があります。
しかし、現代のスマートフォンやタブレットは当時とは比較にならないほど多機能化しており、むしろ審議の効率化に寄与する可能性があります。
委員会室では近年、限定的にタブレットやノートPCの使用が解禁されましたが、スマートフォンは依然として使用禁止です。
2023年には、デジタル担当大臣がスマートフォンを使用しようとして注意を受ける出来事もありました。
この出来事は、国会のデジタル化の遅れを象徴するものとして、多くのメディアで取り上げられ、議論を呼びました。
まとめ:時代に即した国会慣例の見直しは必要か
これらの慣例は、長年の伝統や議会の品位を保つために続けられてきました。
しかし、社会の変化に合わせて見直す必要性も指摘されています。
「くん付け」や厳格な服装規定、電子機器の使用制限など、これらの慣例は本当に現代の国会に必要なのでしょうか?
それとも、議会の伝統として守るべきなのでしょうか?
国会の慣例を時代に即したものに更新することで、より効率的で開かれた議会運営が可能になるかもしれません。
一方で、慣例には意味があるという意見もあります。
今後、これらの慣例がどのように変化していくのか、注目していく必要がありそうです。
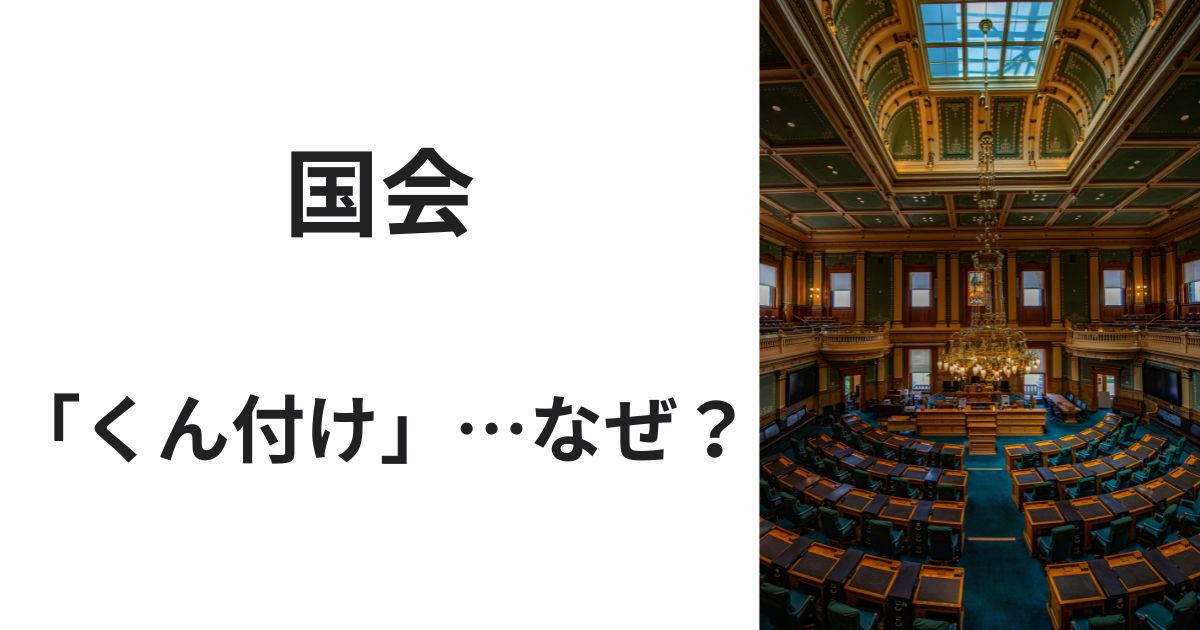
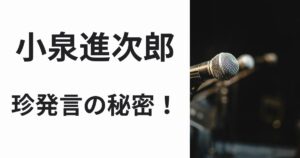
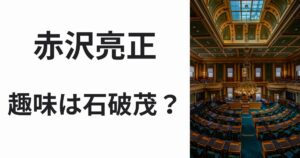

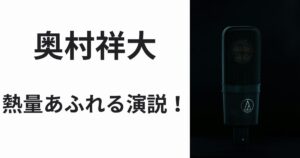
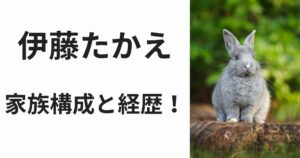
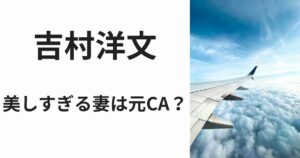
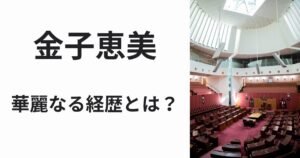
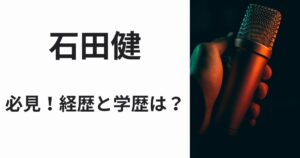
コメント